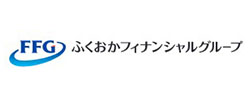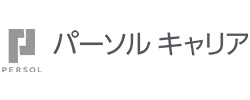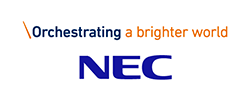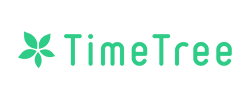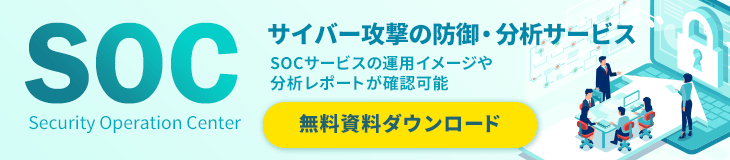サービス・製品
-
脆弱性診断・ペネトレーションテスト
世界トップレベルのホワイトハッカーが調査することによって、標準的な脆弱性診断検出ができないような脆弱性も検出し、リスクを評価します。
詳細はこちら -
GMOサイバー攻撃ネットde診断
WebサイトやドメインなどのIT資産を可視化。国産ならではのわかりやすさと低価格を実現したASMツールをご提供します。
詳細はこちら -
SOC
24時間365日監視のサイバー攻撃防御・分析サービスです。「見直す・見守る・身を守る・みんなで守る」の4つの観点で、お客様と共にセキュリティ運用上の課題解決に取り組みます。
詳細はこちら -
セキュリティインシデント対応支援
セキュリティ事故、インシデントが発生した際の初動対応から、事故原因の特定と再発防止策をご提案します。インシデント発生を想定した事前対策や、トレーニングなどのご支援も可能です。
詳細はこちら -
セキュリティコンサルティング
セキュリティコンサルタントが様々なセキュリティ課題に悩む担当者の方に伴走してご支援します。
詳細はこちら -
セキュリティ訓練/資格取得
サイバー攻撃を熟知した、現場で活躍する講師によるセキュリティ訓練/資格取得サービスです。
詳細はこちら
相談会・セミナー
導入事例
お役立ち資料
ニュース
累計診断実績7,500件ホワイトハッカーの技術力で
お客様のセキュリティ
課題解決をサポート
GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社は国内トップクラスのホワイトハッカーが多数在籍するサイバーセキュリティの会社です。攻撃手法に関する豊富な知識と最先端の技術を持つホワイトハッカーが仮想敵となり、お客様の抱えるセキュリティ上の問題の可視化と課題解決をサポートします。 「誰もが犠牲にならない社会を創る」をミッションとして掲げ、デジタルネイティブの時代を生きるすべての人が安全に暮らせるインターネット社会創りに貢献します。
1位
1位
クラウドセキュリティ部門
*1: 2018年 DEFCON26 Car Hacking Village:世界1位 *2: 2017年 Practical CAN Bus hacking CTF: 国内1位 *3: 当社調査による *4: サイバーセキュリティに関する総務大臣奨励賞を受賞 *5: リンク